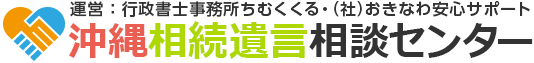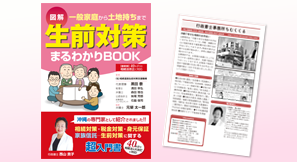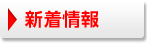2023年05月08日
Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)
那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)
A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。
ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。
相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士が那覇ならびに那覇近郊の皆様の相続を親身にサポートいたします。
2023年03月10日
Q:遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。行政書士の先生にご相談させてください(沖縄)
母の相続について相談があり問い合わせいたしました。
沖縄に長年住んでいる母が先月なくなりました。10年前に父および兄が他界していますので、相続人となるのは、私と兄の子ども達(2人)と思っています。
母の遺産は沖縄の自宅と預貯金です。私は沖縄の自宅に母と一緒に暮らしていたため、自宅をそのままの形で相続し住み続けたいと考えています。しかし、もし法定相続分で分けるとなると、自宅を売却しない限り、兄の子ども達と平等に分けることができません。
兄の子ども達は比較的柔軟に対応してくれそうですが、そもそも遺産は法定相続分で分けなければならないのでしょうか。法律の知識がないため、行政書士の先生にご教授いただけると嬉しいです。
A:法定相続分で分ける必要はありません。話し合いで自由に決めることができます。
民法には法定相続分についての記載があるため、「その通りに分けなければならない」と思う方もいらっしゃいますが、必ずしもその割合で遺産を分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、どのように分けても問題はありません。
今回のご相談の場合、法定相続分はご相談者様が1/2、お兄様のお子様が1人あたり1/4です。しかし、どのように分けるのかは遺産分割協議次第ですので、仮に沖縄の自宅の評価額が2000万円、預貯金が1000万円だとした場合、全員が納得すれば、ご相談者様が自宅を、お兄様のお子様が500万円ずつ相続するというように分けることも可能です。
ただしあくまで全員が合意することが前提です。お兄様のお子様たちが納得しない場合、自宅をそのままの形で相続するならば、ご相談者様が代償金を支払うという方法もあります。
ご相談者様のご希望もあるかと思いますが、一方的に遺産分割案を提示すると、お兄様のお子様たちに不安視される恐れもあるでしょう。まずはお母様の財産全てについてまとめた財産目録や根拠資料をお兄様のお子様たちにご確認いただき、皆様で話し合う場を設けることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄地域の皆様の相続手続きや相続に関するお悩みをお伺いしております。沖縄近郊にお住まいの方で、相続手続きをなにから始めたら良いのか悩んでいるという方は、お気軽にお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターでは初回のお客様について完全無料でご相談をお受けしております。沖縄の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
2023年01月06日
Q:父の相続手続きが必要になりました。戸籍が必要ということは聞いているのですが、金融機関へ提出した際に戸籍が不足していると言われました。何が必要なのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(沖縄)
沖縄の実家の父が亡くなり、相続の手続きが必要になり準備をしています。母も既に他界していて兄弟もいませんので、相続人は私だけです。
先日、父の預金の相続手続きのために沖縄に戻り、銀行へと準備をした書類を持参しましたが、父の戸籍が不足していると言われ手続きが中断しています。持参した戸籍は、父の死亡したことの記載がある戸籍です。これと自分の戸籍を提出しましたが、これ以外に何が必要なのかがわかりません。行政書士は相続の専門家だと聞いたことがありますので、教えていただければ幸いです。(沖縄)
A:被相続人の戸籍は、出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。
相続手続きに必要な戸籍は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。戸籍には種類も多く混乱なさる事も多いかとおもいますが、抜けのないように戸籍を揃えましょう。
一般的には下記の戸籍が必要となりますので、ご確認ください。
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
なぜ被相続人の戸籍が出生から死亡までのすべてを揃えるのかというと、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことをすべて戸籍から読み取り、法定相続人を確定するためです。もし、お父様に隠し子や前妻の子、養子がいた場合は、ご相談者様の他にも相続人がいるかもしれません。相続人が確定しなければ、その後の手続きが進められませんので、早めに戸籍をとりよせて内容を確認しましょう。
戸籍は本籍地のある役所で発行をしてもらいます。通常は、亡くなった方の最後の本籍地の役所へと出生から死亡までの戸籍を請求することでその役所にある戸籍を出してもらう事ができますが、亡くなるまでの間に、引越や結婚などにより本籍地の異動がある場合には、異動前の役所にも戸籍の請求をすることになります。
戸籍は直接窓口での請求だけではなく、郵送での請求も可能ですので遠方に戸籍がある場合には郵送で取り寄せをしましょう。注意点として、従前の戸籍を取り寄せるためには戸籍の記載内容をご自身で読み取り、請求先の役所を見つける必要があります。
今回のケースでは、ご相談者様は沖縄から離れていらっしゃいますので、相続人がご相談者様一人であっても戸籍を全て揃えるためには郵送でのやりとりがメインとなることが考えられます。実際に金融機関へ手続きにいくことも、そう度々帰省できる人ばかりではありません。沖縄での相続手続きにお困りでしたら沖縄相続遺言相談センターがお手伝いいたしますので、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。
9 / 21«...7891011...20...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
無料相談会のご予約はこちら
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階